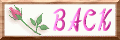聖夜(第3幕)
「ん・・・。ここは・・・?」
そう言って彼女は気が付いた。
まだ、意識は朦朧といしていたが、あたりを見回して自分の状況を確認した。
見慣れない風景だが、少なくとも病院ではないことがわかった。あと、ついさっきまで人がいた気配も読み取れた。
(何かあたし、最後に「病院はやめて・・・」って言ったから・・・?だとしたら、ここは何処?)
仰向けになった体を起こし、彼女は顔に手をあてて思い出そうとした。
(ダメだわ・・・。最後の一言は覚えているのに、何故ここにいるのか・・・)
‘トン トン’
(!!)
突然、扉をノックする音がした。彼女は驚いて、一瞬‘ビクッ’としたが、考えていることを一旦やめて扉の方を見た。
「えっ あっ ど、どうぞ」
いきなりの状況だったのと、扉の向こうの人を待たせてはいけないと思って、あわてて答えた。そのおかげで、しゃべりが、『カミカミ』になってしまった。
「入りまーす」
そう言って、手にお盆をもったバーニィが入ってきた。
「もう、起き上がっても大丈夫?」
部屋に入ったバーニィは、ベッドから起き上がっている彼女を見て心配そうな声でそう言った。
「え、ええ。もう大丈夫よ」
2度目・・・。彼女の声はこれで2度目である。1度目はあのような状況の一瞬だったので、よく聞き取れなかったが2度目は違う。はっきりと聞こえた。温かみのある綺麗な声だった。
「よかったぁ。ちょっと安心」
そう言うと、バーニィは彼女の近くまで来た。ベッドの横にある棚に用事があったようである。バーニィは、お盆をその棚の上に置いた。
「あの・・・ここはど・・・」
「はい、これ。厨房からの戦利品で〜す」
『戦利品』を渡すことに気を取られ、彼女が話しかけたことに、バーニィは気が付かなかった。
彼女は話を聞いてくれなかったことに少し困惑しながらも、バーニィからの『戦利品』であるカップを両手で受け取った。カップの中身は、飲まなくても匂いで分かった。カップからは、美味しそうなスープの匂いがしていた。
「ありがとう・・・。えっと・・・?」
「あっ、ごめん。初めてなのに、自己紹介がまだだったね。僕はバーナード・ワイズマン。みんなからは『バーニィ』って呼ばれています」
バーニィはそう言うと、右手を彼女に差し出した。
「私は『クリス』。クリスチーナ・マッケンジー」
クリスと名乗った彼女は、差し出したバーニィの手を取り、握手した。
「スープ、ありがとうバーニィさん。えっと・・・、ところでここは何処?」
一口、カップのスープを飲むと、先ほど言えなかった質問をした。
「え?! あっ、ゴメン。説明がまだだったね。ここは、ホテル・アスシズ。僕のアルバイト先で、この部屋は、社員の仮眠室です。」
頭を‘ポリポリ’掻きながら、困った表情とあせった表情で、質問に答えた。
クリスは、小さな声で‘クスッ’と笑った。
「ごめんなさい。助けてもらった貴方に笑うつもりはなかったのだけど、表情がおかしくて・・・。それに、まぶしかったから・・・」
「えっ?それに・・・何?」
最後のセリフが小さな声だったので、聞き取れなかった。
「ん!な、何でもない」
笑いながら、両手を左右に‘ブンブン’振って否定した。
バーニィが見ても、何かを隠しているのは明白だった。しかし、そんなことは、バーニィにとってはどうでもよかった。クリスが笑ってくれたので、それでよかったのである。
「少し、元気が出たかな?よかった・・・」
それだけ言うと、笑顔から一転して鋭い真剣な表情になった。クリスもバーニィのその表情を見ると、これから言わんとしていることが予想できた。
「あの、クリスさん・・・。どうして・・・」
「あのね・・・」
最後まで言い終わらないうちに、クリスが話し出した。
「あのね、あたし精神的にちょっと参ってたんだ・・・。」
「精神的・・・に?」
悲しみの表情でうつむきながら話すクリスに、心配そうにバーニィが言った。
「あたしね、こう見えてもピアノを弾きながら歌も歌える歌手なんだ。今はクラブ歌手だけど、一応プロ志望・・・なんだ」
クリスは笑顔で言ったが、それが無理をしているのがバーニィにもわかった。
「でも勤め先のクラブから『お前はもうクビだ』な〜んて言われて、何日もヘコんでたの。急に言われたから・・・」
笑顔が段々と消え、少しずつさっきの悲しい表情に戻っていった。
「で、何か別の仕事を探したけど見つからない日々が続いて・・・。最後に『どうにでもなれっ!』って思ったとたん、急に意識が無くなったの」
クリスのセリフに、バーニィの表情が変わった。
「多分、『病院はやめて』って言ったのは、お金が無いからかな・・・?ほとんど本能っていうか無意識だったから、なんでそんなことを言ったのか、正直あたしもよくわかんないんだ」
最後の方は、言葉強く笑顔でバーニィの顔を見て言ったが、先ほどと同じく空元気だった。クリスも、バーニィの表情を見て一瞬で笑顔を解いた。
「あの、クリスさん・・・。こんな事を僕が言うのも変ですけど・・・『どうにでもなれっ』って考えは、止したほうがいいです・・・」
真剣な顔で言った。
「確かに世間は立ち直ったばかりで苦しいですが、そんな後ろ向きじゃダメですよ」
クリスはバーニィの目を‘ジッ’と見つめながら、話を聞いている。」
「『どうにでもなれっ』ってそんな悲しいこと言わないで下さい。諦めたらそれで終わりじゃないですか」
少し声に、涙が混じった。
「・・・初対面なのに言ってくれるじゃない」
突っぱねるように、クリスが言った。
「じゃあ、あたなには何か夢があるの?」
「僕の夢・・・?」
過去を振り返るように、遠い眼差しで話し出した。
「僕の本当の夢は、学校を卒業してジオニックに入社して「ザク」をいじることだったんだ・・・。でも、ティターンズ政権の崩壊のゴタゴタで卒業できなかった・・・」
そこまで言うと、クリスに背を向け部屋の中の椅子に腰掛けた。
「別に、政権崩壊を恨んでいるわけじゃいよ。今のほうが断然住みやすい世の中だからね。でも・・・」
体だけクリスの方に向きなおし、さらに続けて言った。
「僕の夢を閉ざした原因の一つには変わらない・・・。だからと言って、夢の全てを閉ざした訳じゃない」
バーニィは拳を作り、力を入れて話した。目つきも先ほどの「遠い眼差し」から「真剣な熱い眼差し」に変わっていた。
「今はここでバイトをしながら、整備工場の見習いもしているんだ。そこでは、「ザク」以外にも、いろいろなマシンに触れる。今は、逆にこっちの方がイイと思ってる」
最後は、満面の笑みをクリスに向けた。
「結果的に言えば、僕は夢を諦めたことになるけど、でもクリスさんには諦めてほしくない・・・。」
最後まで、真剣な表情とだった。
「ごめんなさい・・・。言い過ぎですね・・・」
その一言だけは、言葉が弱かった。
「あたしの方こそ、初対面のあなたにキツイ言い方をしたわ。ごめんなさい」
体を起こしている状態で、バーニィに向かい‘ペコリ’と頭をさげた。
バーニィは‘気にしないで’といって、手を左右に振った。が、何でクリスが謝ったのかちょっとよく分かっていないようだ。顔が困惑している・・・。
「バーニィさんの言うとおり、諦めたらそれで終わり・・・だしね。それにまだ若いしチャンスだって何度もあるし・・・。簡単に諦めないようにするわっ!」
腕を握りこぶしにて、最後の方と『若い』の部分は、声を大きく力強く言った。
「プッ、あはははは」
「フフッ あはははははは」
クリスの言い回し方に、思わず吹き出してしまったバーニィと、そのバーニィと自分のセリフに笑ってしまったクリスは、声をあげ、心のそこから笑っているようだった。
「本当にありがとう、バーニィさん」
先に笑い終わったクリスが、またバーニィに対して頭を下げた。
「なんだか、バーニィさんに元気を分けてもらったみたい。ありがとう」
「そ、そんなこと・・・。僕の方こそ、初対面のクリスさんにキツイ言い方をしてしまって、申し訳ない」
初め照れたそぶりを見せて、そのあとペコリと頭を下げた。
「ううん。そんなことないわよ」
左右に首を振りながら、答えた。長い髪がサラサラと揺れる姿は、少し幻想的な感じを受けた。
’何かヒカリが見えた’。バーニィには、そのような姿が見えたような気がした。
「でも、あたしもいつまでもこのバーニィさんの優しさに甘えてる訳にはいかないから・・・」
さっき首を振ったことで乱れた髪を直しながら、言った。その手つきは、当然慣れており、ごく自然だった。バーニィはその仕草の一つ一つに、ドキドキしていた。
(何、緊張してるんだろ僕・・・。やっぱおかしいよな、今日の僕・・・)
「あたし、そろそろ行くね」
体を起こした状態から、両足を地面について、体ごとバーニィに向けた。
「ん?じゃぁ・・・」
そういうと、バーニィは掛けてあったコートとクリスが持っていたカバンをクリスの所に持っていった。
「あっ・・・。わざわざいいのに。ありがとうバーニィさん」
クリスは立ってそれを受け取った。お互い、初めて近くで顔を見た瞬間だった。
(あら〜、近くで見るといい男ね。って、あたしったらこんな時に何を考えてるの?!)
顔を赤らめてしまったクリスは、顔を下げてしまった。
バーニィもクリスの顔を近くで見てしまったので、顔を赤くして照れてしまった。
「・・・もう、行くね」
互いに顔が赤らめている中、クリスが最初に口を開いた。サッとコートを着て、長い後ろ髪をコートの外に出した。その姿は、TVに出てくる女優のようで、綺麗でなめらかな仕草だった。バーニィは、またその仕草に魅了された。
「あっ、このカップは?」
「・・・えっ!?あぁ、ぼ、僕が片付けておきます」
クリスの仕草に見とれてしまい、会話が少し遅れた。
「ありがとう、あたしの為に厨房から・・・」
「そんな、気にしないでくださいよ・・・」
そこまで言って、バーニィは言葉を飲んだ。
「あ、あの・・・女性が夜一人で帰るのはキケンだから・・・そのもし・・・」
「ありがと、バーニィさん・・・。でも、いいの?彼女さんとかいるんじゃない?」
バーニィが話し終わる前に、クリスがいたずらっぽく笑って言った。
「いえ、彼女なんて・・・。恋人いない暦、年の数ですから」
頭を‘ポリポリ’掻きながら言った。最後の方は力なく、声がだんだんと小さくなっていった。
「ごめんなさい。そんなつもりで言ったんじゃなくて・・・。送ってくれるんでしょ?もちろんOKよ。」
「えっ?!」
言わんとしていた事が読まれたことと、意外と即答だったこと、そして返事がOKだったので驚いてしまった。その驚きが、表情にも出てしまった。
「何よ、その顔は〜」
顔を‘プ〜’っと膨らませてバーニィを見た。
「あ、え、ゴメン。ほらクリスさんこそ、恋人がいるんじゃないかと思って・・・。話、最後まで言えなかったから・・・聞けなかったし・・・」
途切れ途切れで、バーニィは言った。
クリスが顔をのぞきこむと、思いっきり赤面している。
(あらら、かわいい所、あるじゃない)
「あはは。あたしだってバーニィさんと同じ、イナイ暦年の数よ」
バーニィとは違って、明るく笑って答えた。
「そ、そうなんですか?」
意外そうな表情で、バーニィは答えた。
「で、レディを何時まで待たせる気?あたしはもう出られるわよ」
先ほどと同じく、いたずらっぽく言った。だがそれは2度目に聞いた、温かみのある口調と笑顔付である。
「あっ、僕もすぐ準備をします。カップを厨房に返してきますね」
「うん、わかったわ。じゃあ、あたしがこの部屋を片付けておくね」
「えっ、悪いよそんな・・・」
「いいのよ。どうせ待ってる間、暇だから」
「じゃぁ、お願いしますね」
‘ペコリ’と頭を下げると、手際よくカップを持ってきたお盆に乗せた。
「クリスさん、お願いしますね」
と言ってクリスに対し手を振って、部屋を出た。
「早く帰って来てね」
クリスは、そう言ってバーニィを見送った。バーニィには聞こえていなかったのか、その後の返事が帰ってきてない。
(あら、やだ。あたし何をいってるの?)
クリスは、自分の発言に困惑してしまったが、悪い気はしていなかった。むしろ少し心地よいものを感じていた。
―あとがき―
現在、6日の金曜日です。20日を切りました。
本当にヤバイです。時間が掛かりすぎです。
間に合わなかったら、終わってからでもいいかな?(爆)
よくないですよね。(笑)
とりあえず、この3幕まで上げようかな?
あと1幕で終わるかもしてませんので・・・。
この1幕は、ハッキリ言って原作でも覚えていないところの部分も含みます。
上手く書けるか、それはもう運しだいです。(爆)
そしてクリスマスに間に合うかどうかは、神のみぞ知るです。(核爆)
自分にファイト!(またかよっ!、笑)
NEXT EPISODE へ